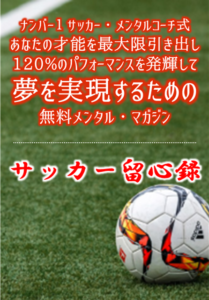サッカーやスポーツにおける “メンタル” と“コミュニケーション”
メンタルにコミュニケーションは関係なさそうに思えますが・・・ これは、ものすごく関係性が高い。
“メンタル”という言葉が至るところで使われ、その重要性を認識し、実感もしている僕たちメンタルコーチからすると、それはとても嬉しい状況だ。
ただ一方で、あまりにも、“メンタル”という言葉が日常的に使われることで、言葉の定義が正確になされないまま、時には本来の“メンタルというものの定義”とはかけ離れた意味合いで使われる場面に遭遇することも多いとも感じている。
僕たちの扱う “メンタル”の領域は広く、その中の要素として “コミュニケーション”や“関係性” とも含まれる ということを、ここではまずお伝えしておこう。
では、なぜ、コミュニケーション力や仲間同士の関係性がパフォーマンスにも影響するのか。
一見すると、“メンタル”と“コミュニケーション”には、なんのつながりや関連もないように思えるかもしれないが、実は、とても深い関連がある。事例を見ながら、一緒に考えてみてほしい。
- 西野監督の“選手の力を引き出す”コミュニケーション
- 堂安選手の“仲間に認められる”コミュニケーション力
- すべての事柄に影響してくる“コミュニケーション”
■西野監督の“選手の力を引き出す”コミュニケーション
2018年のワールドカップで、日本代表は過去に例をみない、本番2ヶ月前での監督交代 という勇気ある決断をした。
結果論かもしれないが、西野監督になったことで、代表選手たちは生き生きと自分の特徴を発揮していたように感じた。
様々なメディアでも盛んに、西野監督のリーダーシップが取り上げられていたが、その成功要因の中の一つが「選手と監督、スタッフがお互いに円滑なコミュニケーションを図れたこと」 と言える。
コミュニケーション能力といっても様々なコミュニケーション手法やアプローチの方法があるが、西野監督の場合は、“引き出す対話型コミュニケーション”と言える。
どの方法のコミュニケーションが良くて、どの方法は悪いということではなく、その時々に変化するチーム状況により、マネジメント方法やコミュニケーション手法は変化させるべきものだ。なぜならば、それらの“手法”は、あくまでも手法であり、目標や目的を達成するための手段に過ぎないからだ。
それを前提に解説するならば、前監督のコミュニケーション手法は、わかり易く言うと、トップダウン型で変化のない手法を貫いていた。監督が「試合に勝つ」ための戦略やゲームプランを組み立て、そのゲームプランを実現できるメンバー選考を行う。選手たちの意見も聞くが、基本的に監督の考えが絶対。
西野監督は、ボトムアップ型とトップダウン型の中間。勝つためのゲームプランをもちながら、選手たち “現場”の感覚も吸い上げ、それらをミックスさせて、最良の戦術を練り実行する。
監督交代から本番までにわずか2ヶ月という、わずかな準備期間しかない中では、通常、“トップダウン型” の方法を選択することの方が多いだろう。しかし、西野監督の方法だったからこそ、2018年のワールドカップの成績へと導いた。
結果的に、今回の日本代表メンバーにとっては、西野監督の方法の方が、持てる力を存分に発揮しやすかった、ということになる。
西野さんから、ガンバ大阪時代に指導を受けた、元日本代表GK・本並健治さんは、解説の中で、
やはり選手同士のコミュニケーションです。
よく話すようになって、選手に自主性が生まれました。
監督もそれを容認していて、すり合わせができて、
コミュニケーションが細部まで行き渡っているようです。
と印象を述べている。
■堂安選手の“仲間に認められる”コミュニケーション力
2018年ワールドカップの日本代表メンバーにも選ばれるのでは!? と、メディアにも取り上げられた、将来の日本代表のエース候補の一人、堂安律選手(19)。
昨年6月23日にガンバ大阪から、オランダ・フローニンゲンへの移籍が発表されてから約1年が経過。ヨーロッパで過ごす初のシーズンで、堂安選手は、リーグ戦29試合出場9得点という堂々たる結果を残した。その結果が評価され、代表候補としても注目される存在になったのだ。
その堂安選手のインタビューが掲載された雑誌「Number Web」には、コミュニケーションに関する内容も含まれており、海外でも成功するエッセンスをピックアップしてみた。(「堂安律、その野望を大いに語る」より引用 )
それによると、結果を出すため、チームの信頼を得るためのアプローチとして、
- オフ・ザ・ピッチで積極的にチームメイトとたくさんコミュニケーションをとったこと。
- 言葉の壁で、人との距離を縮められず、それがオン・ザ・ピッチにも影響し、最初の3、4カ月が難しい時期になったこと。
- チームに馴染めていない時期は、試合に出てもボールが来ないので、練習で自分を信頼してもらう努力を欠かさなかったこと。
- 日本とは異なり、試合に出られなかった時、自分が求めなければ、周りは突き放すのが外国。
- だから、試合に出れなかった時、自分から「自分に足りないものはなにか」「監督が自分に期待しているものはなにか」を考え、自分でわからなければ、監督に聞きに行くことができるかどうか。
- 実際、4、5試合試合に出れなかった時、監督に聞きに行き、それを基に練習に取り組んだら、試合に出させてもらえるようになったこと。
と、綴られている。
日本人が海外に行き、まず苦労するのが、言葉の壁も含めたコミュニケーションと言われる。実際、チームメイトやスタッフ、監督やコーチなどとコミュニケーションがうまくとれず、良好な関係性も築けず、結果として、自身の選手としての特徴や長所をパフォーマンスとして発揮できずに帰国した選手は何人もいる。
特に、海外では、“自分から”主体的に他人との関わりを積極的に取れなければ、何を考えている人なのか、相手に伝わらないし、相手が来るのを自分が待っていても、何も起こらない。しかも、言葉そのものが通じないというハードルがある。
堂安選手が、オランダのチームへ移籍してから行ってきた数々の行動や、それにともなう思考や考え方は、たとえ海外でなく日本国内だったとしても、チームスポーツであるサッカーという競技にとって、大切な要素が数多く詰まっているのではないだろうか。
■すべての事柄に影響してくる“コミュニケーション” (まとめ)
さて、では、どうして、“メンタル”に“コミュニケーション”が関係してくるのか。
2018年のワールドカップに選ばれた日本代表選手たちは、自分自身の考えを指揮官に伝えることができ、更に選手同士での意見交換やディスカッションも良しとされていたこともあり、チーム内にはきっと、「このチームでは、自分の感じたことや考え、意見が遠慮なく言える!」 と実感していたことだろう。
この感覚は、良いチームにとって、とても大切なエッセンスだ。なぜならば、ピッチの上でサッカーをするのは選手たち自身であり、一人ひとりのプレーヤーが、瞬間瞬間の判断を積み重ねながら、仲間とともにプレーするのがサッカーというスポーツである以上、主体性なくして、強いチームを造ることは難しいことで、試合の中では必ず、選手一人ひとりの考えや思考が嫌でも反映されてしまう。だからこそ、自分自身の考えを“目標達成のために”闊達に言える空気感のあるチームは強くなるのだ。
西野監督始め、日本語でコミュニケーションがとれる日本人スタッフだったこと、そして、西野監督が、対話型のリーダーシップで、選手たちの考えや意見に耳を傾けたことで、「この監督は、自分の意見を否定するんじゃなく、耳を傾けてくれる人なんだ」 という良い空気感がチームに生まれ、“安心して”コミュニケーションが図れる関係性を築くことができたのだろう。
それらの雰囲気によりもたらされる心理的要素として、
“安心感”
“自己受容感”
“所属感”
“前向きで肯定的な関係性”
などの、“感覚” を持てることにつながり、“心の状態” にも良い影響を及ぼし、その結果、素晴らしいパフォーマンスへつながったのだ。
それとは逆にもし、
「ここでは自分の考えを言っても、否定されるぞ」
「自分が感じたことを言っても、耳を傾けてくれない」
「監督や指導者の言う通りにしたり、望むプレーができないと選ばれない」
などの負の感情、否定的感情、などのマイナスの感情につながっていたら、それは、心の状態にも影響し、さらには、パフォーマンスにも影響を与えていたと考えられる。
さらには、堂安選手の事例のように、 “仲間との関係性” が良い方向へ進み、 “監督やチームメイトの考えも理解できる” 素晴らしい状況を築くことができれば、自分がどのような特徴をだし、どんなプレーをすれば良いかのお互いの理解も深まるので、結果として、試合でのパフォーマンスにもつながったと言える。
逆に、もし、言葉もしゃべれず、言葉が通じないからと、仲間とも打ち解けず、監督やチームメイトが何を期待し、どんな考えなのかもわからず、、、という状態だったならば、どんなことが起こるかというと、あくまでも予想だが、
孤独感が増し、
自分勝手なプレーとなり、
チームスポーツなのに、仲間と意思疎通や連携図れず、信頼もされないので、悪いパフォーマンスへつながり、
結果、チームを去る、
ということになっていたかもしれない。
そもそも、サッカーという競技に限らず、そして、スポーツに限らず、どんな人も必ず、なんらかの組織やグループに所属し生きていますし、人と人との関わりや関係性の中で、生きている。そして、一人では生きてはいけない。
だから、 誰かと関係を築いたり、コミュニケーションを図るということは、人間が生きていく上でも大切な要素。心の状態にも影響してくるのは当たり前 のことなのだ。
選手として、あるいは指導者として、何かしらの“結果”を出すには、コミュニケーション能力は欠かせない要素。
そして、それはまた 心の状態=メンタル にも大きく影響を及ぼしているのだ。